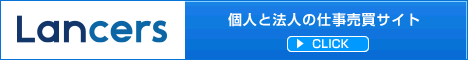F工場の軌跡
子沢山な母だった。44年がむしゃらに働いた。誰からも愛された。しかし歳をとり、別れの時が近づいていた。2014年に解体が決まったマツダの母なる工場「F工場」のことである◆1960年発売のマツダ初の四輪乗用車「R360クーペ」を皮切りに、2004年までに産み出した車は一千万台。日本初のコンピュータによる生産管理や世界初の電着塗装など先進技術で後続工場の範となった特別な工場であった◆だからこそ、F工場出身で、奇しくも解体工事を任されたプラント技術部長の岩本は、解体ではなく勇退としての花道を用意したかったのだ。それは工場を傷つけず、怪我人を出さず、近隣にも迷惑をかけない工事。そこで工事関係者全員にその想いを伝え、「F工場は最後まで見事だったと思われる送り方をしたいんです」と頭を下げたのである◆岩本の想いに、工事関係者は応えてみせる。生産設備はあえて組立順序を逆に辿って慎重に分解した。常に騒音装置を確認し、廃材を置く音にも気を配った。高所作業の際はまず地上で予行演習した。「まるでおくりびとの気持ちで臨んだ」と、ある作業員は述懐している。こうして建設時の倍の2年4カ月を費やし丁寧に工事を進めたのだった◆徐々に終わりが近づくにつれ、関係者が続々と訪れた。F工場出身の社長鳥飼正道もその一人。別れの挨拶がしたいと駆け付けた彼は、若き日に汗を流した場所を黙って見つめるとぽつりと呟いた。「ありがとう」◆そして2017年7月、そぼ降る雨の中、遂に最後の柱はゆっくりと倒れていったのだ。工事の陣頭指揮をとった岩本の、涙に滲む視線の先で、F工場はその生涯を閉じたのである◆確かにF工場の姿はもうないが、その精神は永遠のはずだ。「頑張りなさい。いいモノを作りなさい。諦めなければ大丈夫」。壁にぶつかった時は、あの母の声を聞け。
広島とマツダ
その日、広島平和大通りを埋めた30万人の観衆がいたる所で掲げたのは、家族の遺影であった◆1975年10月15日、広島東洋カープ初優勝パレード。「じいちゃんが喜んでるよ~」「ばあちゃんが待ってたぞ~」。涙の笑顔でそう叫ぶ彼らの姿を、パレードの車上から目にした山本浩二や衣笠祥男らはこみ上げるものをグッとこらえて手を振り返した。原爆投下から30年目の奇跡であった。草木も生えぬと言われた広島に球団が誕生したのは、終戦から僅か4年後の1949年。復興を象徴する市民球団として期待されたものの、最下位争いを繰り返し、経営難で観客の樽募金に支えられる程だった。しかし負けても負けても立ち向かう姿に、人々は戦後の混迷から這い上がる自らを重ね、一勝一勝に希望を見出してきたのである◆創設13年を経ても財政難が続くカープを救おうと1962年に球団社長を引き受けた三代社長・松田恒次にも逸話が残っている。開発費の融資を受けるべく、銀行の頭取と会合した時のことだ。「カープを見てやるとは、ゆとりがあるんですね」という頭取の皮肉に「道楽で見ようというのではありません」と気色ばんだのだ。そして続けた。「原爆で親子や兄弟を失い、その悲哀を晴らす場所さえ失った市民にとって球団は唯一の慰みの場。黙って消滅を見過ごす訳にはいかんのです」。当時はロータリーエンジン量産化で大変な時期だったが、それでも地域の希望の灯は消さないという恒次の信念を知り、頭取は即座に頭を下げたと言う◆悲願の初優勝を見ることなく恒次は1970年に没するが、あの優勝も、後に常勝軍団となる未来も、どこかで確信していたのではないか。被爆を経験したある婦人が、初優勝に涙してこう語っている。「生きるとは、諦めたらいかんということ」。その通り、諦めなかった人生にある日咲く、真っ赤な花の美しさよ。
渡し船
真っ青な大空を猿猴川が映していた朝だった。川沿いの船着き場では、マツダ の連絡船・仁保丸が定刻の出航を待っていた。8時15分。「時間だ」「よし出航」。鈴木と田中、船頭同士のいつもの会話。ただ一つ違うのは、今日が最後の運航日ということだった◆1958年から17年、本社と渕先工場を結ぶ交通手段として、月間1万人の社員を送迎してきたのがこの連絡船だ。しかし仁保橋や東洋大橋の竣工で役目を終える時が来たのである◆いつも通り渕崎へ漕ぎ出しながら、鈴木が思い出していたのはあの日のことだ。「誰か川に落ちたぞ~」。岸からそう叫ぶ声に振り向くと、ボートが転覆し父子がおぼれている姿が見えた。咄嗟に船を向けると、川の中から父が息子を掲げ、必死に鈴木へと手渡してきた。無事二人とも救出したがあの子は幾つになったろうか。命の重みを今も手が覚えている◆一方の田中が苦笑交じりに思い出していたのは60年代の通勤ラッシュだ。「朝礼に間に合わない」と船に飛び乗った勢いで、浅瀬に落ちた社員を何度拾い上げたかしれない。そうそう、船が川中で故障した時は、予備船を泳いで取りに行ったっけ。懐かしさの中の一抹の寂しさ。だが何より二人の心を占めていたのは、自分達にしかできない仕事を全うしたという誇りであった◆本社から渕崎へ、渕崎から本社へいつも通り40往復。そして16時50分、遂に本社発最終便を終えようとする時だった。そこには予想外の光景があった。夕闇迫る渕崎工場から大勢の人が溢れ出して帽子を振っているのだ。朝夕よく見る顔、顔、顔。17年の仕事が報われたと感じた瞬間だった◆一隅を照らす。一つの仕事に徹して世に貢献するという意味だが、歴史からひっそりと消えた彼らもまた一隅を照らした宝であった。その功績に感謝し、ここに記しておく。汗と重油と川風にまみれた男達の物語を。